
「友達にすすめられた整体に通ってみたけど、私にはあまり合わなかったな…」なんて経験はありませんか?あるいは、同じように「肩こりがつらい」と言っていたのに、人によってアドバイスされる対処法が全然違った、ということも。
実はこれ、東洋医学の世界で昔から大切にされている考え方、「同病異治(どうびょういち)」という言葉に通じているんです。
また、逆に「全く違う症状なのに、同じ漢方薬を飲んで良くなった」「ヨガを始めたら、不眠も生理痛も落ち着いた」なんてこともありますよね。これもまた「異病同治(いびょうどうち)」という、興味深い考え方に関係しています。
今回は、そんな2つの言葉に込められた意味と、それが私たちの日々の健康やセルフケアにどう活かせるのかを、わかりやすくご紹介していきます。

同病異治とは? 同じ症状でも、治し方は人それぞれ
まず、「同病異治」について、ご説明します。
これは文字通り、「同じ病気であっても、一人ひとりの状態によって治療法は異なるべきである」という考え方です。
例えば、「頭痛」に対して、西洋医学では「風邪」という診断がつけば、基本的には風邪のウイルスに効果のある薬が処方されます。もちろん、患者さんの状態に合わせて薬の種類や量を調整したり、対症療法を行ったりしますが、病名と原因に基づいた治療が中心となります。
一方、東洋医学では、たとえば同じ「頭痛」でも、その原因が冷えから来ているのか、ストレスから来ているのか、あるいは目の疲れから来ているのかによって、選ぶ薬やケアの方法が変わってきます。
漢方や東洋医学では、「病気を治す」のではなく、「その人自身を整える」ことを大切にします。だからこそ、同じ症状でも、その人の体質や生活環境、心の状態によって、治し方は一人ひとり違って当たり前なのです。
女性特有の症状とも言える「冷え性」「便秘」「生理痛」なども、まさにこの考え方が役立ちます。「友達には○○茶が効いたけど、私には△△湯のほうが合っていた」というのも、同病異治の典型的な例です。
異病同治とは? 異なる病気でも治療法は同じ
次に、「異病同治」です。「異病同治」は、「異なる病気でも、同じ治療で改善される」という考え方です。
例えば「不眠」と「イライラ」「動悸」といった一見バラバラな症状も、実はストレスや自律神経の乱れが共通の原因だった、ということはよくあります。
この場合、心を落ち着ける漢方や、リラックスできるアロマ、呼吸を整えるヨガなどが、それぞれの症状に対して効果を発揮することがあります。
また、西洋医学でも、1つの薬が複数の病気に効くことは珍しくありません。たとえば、「うつ病」と「過敏性腸症候群」に使われる薬が同じだったりするのも、異病同治の一例と言えるでしょう。
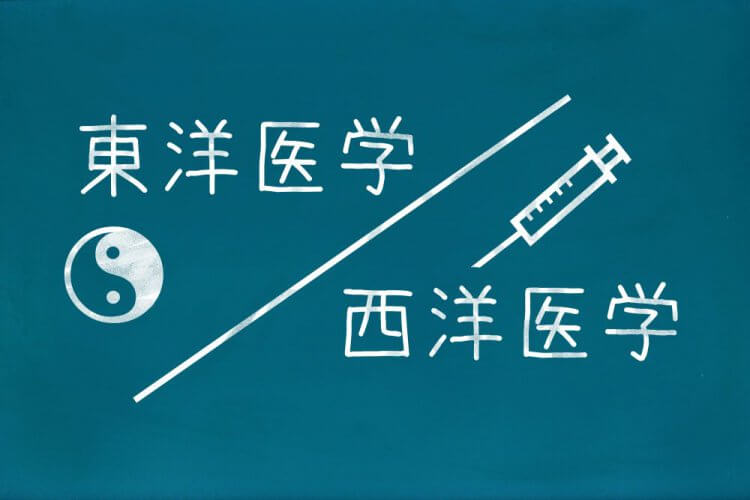
二つの概念の関連性と東洋医学の診察
「同病異治」と「異病同治」。同じ病気なのに違う治療、違う病気なのに同じ治療。一見すると矛盾しているように思えるかもしれませんが、実はこの二つは、東洋医学の根幹をなす「病気そのものよりも、病気にかかっている人を診る」という哲学に基づいた、表裏一体の考え方なのです。
どちらの概念も、「病名」という表面的な情報だけでなく、その人の体質 など固有の体の状態を正確に把握することが治療の鍵であることを示しています。
東洋医学の診察では、「問診」 で症状だけでなく生活習慣や精神状態、既往歴などを詳しく聞くのはもちろん、
「望診(ぼうしん:顔色や舌の状態を見る)」
「聞診(ぶんしん:声の調子や呼吸音を聞いたり、体臭を確認する)」
「切診(せっしん:脈やお腹の状態に触れる)」
といった「四診」を駆使して、全身の状態を総合的に把握し、「証」を見極めることに時間をかけます。この「証」こそが、治療方針を決定するための最も重要な情報となるのです。
現代社会における意義
画一的な情報があふれる現代社会において、この「同病異治」「異病同治」の考え方は、私たち自身の体と向き合う上で非常に重要な示唆を与えてくれます。
たとえば、友達がすすめてくれたダイエット法が自分には合わなかったとき、「私のやり方が間違っているのかも」と落ち込むのではなく、「体質が違うから、私には別のアプローチが必要なんだ」と考えることができます。
また、「なんだか最近、いろんな不調が出てきた…」というときも、体の中にある共通のサイン(ストレス、冷え、栄養不足など)に目を向けてみることで、根本的なケアにつながるかもしれません。
自分の体にやさしく耳を傾けること。それが、同病異治・異病同治の最も大切なポイントです。

「同病異治」と「異病同治」。これらは、伝統的な東洋医学が長い歴史の中で培ってきた、病と向き合うための深い知恵です。病名という枠にとらわれず、私たち一人ひとりの体が持つ固有の体質や状態、そして病気の根本原因に目を向けることの重要性を教えてくれます。
あなたの体は、あなただけのものです。画一的な情報に惑わされず、ご自身の体の声に耳を澄ませ、その状態を正しく理解しようとすること。
そして、必要に応じて、病名だけでなく「あなた自身」をしっかり診てくれる医療やケアを選択すること。東洋医学の知恵は、健康で自分らしい毎日を送るための、大切なヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

※ オリーブ油・ホホバ油・ヒマワリ種子油
(毛髪保護成分・浸透成分・保湿成分)
recommended posts
-

vol.172 サステナブルなライフスタイルを。循環型社会を考える~ドイツで始まっているデポジット制度とは~
2021.12.10
-

vol.470 半身浴の効果を高める方法は?相性がいい4つの美容法を紹介
2024.11.08
-

vol.121 日本のフードロスへの取り組みと、今日、私たちにできること
2021.07.15
-

vol.606 冬は夏より基礎代謝が上がりやすい?寒い季節を味方につける生活習慣
2026.01.28
-

vol.207 女性の魅力を高めてくれるイランイラン。エキゾチックで甘い香りに含まれている効果効能は?
2022.04.01
-

vol.379 肩甲骨のコリが呼吸を浅くしているかも!?肩甲骨をほぐして深い呼吸をしよう
2023.10.24
-

vol.040 カーサフライン・ディレクター 石井瑛真さんインタビュー 第2回
2020.10.27
-

vol.346 スーパーフード「抹茶」が持つ美容・健康パワーは!?リラックスもできる抹茶の効果・効能
2023.06.26
-

vol.028 ストレスフルな私たちの日常に
2020.08.25
-
vol.172 サステナブルなライフスタイルを。循環型社会を考え・・・
column | 2021.12.10
-
vol.470 半身浴の効果を高める方法は?相性がいい4つの美容・・・
column | 2024.11.08
-
vol.121 日本のフードロスへの取り組みと、今日、私たちに・・・
column | 2021.07.15
-
vol.606 冬は夏より基礎代謝が上がりやすい?寒い季節を味方・・・
column | 2026.01.28
-
vol.207 女性の魅力を高めてくれるイランイラン。エキゾチ・・・
column | 2022.04.01
-
vol.379 肩甲骨のコリが呼吸を浅くしているかも!?肩甲骨を・・・
column | 2023.10.24
-
vol.040 カーサフライン・ディレクター 石井瑛真さんインタ・・・
INTERVIEW | 2020.10.27
-
vol.346 スーパーフード「抹茶」が持つ美容・健康パワーは!・・・
column | 2023.06.26
-
column | 2020.08.25









