
12月に入るとすっかり日が短くなり、気づけば夜が長くなっています。12月はクリスマスや大晦日などの楽しいイベントがたくさんありますが、そのうちの1つにある「冬至」。
毎年、12月21日か22日にやってくる冬至。
冬至という名前しか知らない方もいるかもしれませんが、今年の冬至はいつなのか、冬至に向けてどのような準備が必要なのか、日本の四季を感じつつ、冬至についてみていきましょう。

冬至とは
冬が至ると書いて冬至。冬至とは、二十四節気のひとつで、北半球において一年の内の一番昼の時間が短くなる日のこと。
夏の「夏至」が終わって、秋を越え、冬になり、どんどん日が短くなっていきますが、この冬至を境に昼間の時間が少しずつ長くなっていくことから、冬至は太陽が生まれ変わる日ととらえ、自然界の生命力が回復する節目とされ、古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われています。
また、冬至は風水的に「陰が極まり再び陽にかえる(一陽来復)」と言われ縁起がいい日とされています。
「陰が極まり再び陽にかえる冬至は、運気が切り替わり、すべてが上昇運に転じる日」、「悪いことばかりが続いていたのが、ようやく善い方に向いてくる」という意味もあります。
冬至の日程は年によって異なる
冬至は毎年同じ日というわけではなく、12月22日前後で年によって異なります。ちなみに、今年2021年の冬至は【12月22日】、来年2022年の冬至も【12月22日】です。
世界の冬至の過ごし方
北欧では、昔、冬至の頃に「ユール」という祝祭が行われ、ユールで薪を燃やして悪霊を払う行事が行われていた名残が、現在のクリスマスケーキ、ブッシュ・ド・ノエル(薪の形のケーキ)となって残っています。今でも北欧諸国ではクリスマスのことをユールと呼ぶことがあるのだとか。
また、「クリスマス」はキリストの誕生日だと言われていますが、実はケルト人が「冬至を祝ったお祭り」が発祥だともいわれています。
中国では冬至はとても大切にされていて、餃子や餡入り餅、小豆を煮たぜんざいのようなものを食べる風習があったり、台湾や中国の南部では「湯圓」(たんゆえん)というお団子のような料理を食べるのが伝統として残っていたりします。
運を呼び込む日本の冬至の過ごし方
日本における冬至の過ごし方は、以下のものが有名です。
①「ん」のつくものを食べて「運」を呼び込む
冬至には、運気が上がる「ん」がつく食べ物を食べるという風習が、日本各地にあります。この「ん」のつく食材を食べるのは「運盛り」と言って、「運」をさらに上昇させようと縁起を担いでいたのです。
特に、「ん=運」が二つ重なる食材は、運気が2倍になって縁起がよいとされています。
「ん」が2回つく食材7種類、なんきん(かぼちゃ)、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん(うどん)を指して「冬至の七種」と呼ぶこともあります。
冬至は、かぼちゃを食べることで有名で、かぼちゃを食べると、風邪をひかないと伝えられています。
なぜ、かぼちゃかご存知でしょうか?
かぼちゃの原産地は中南米の暑い国の野菜。カットさえしなければ、風通しのいい涼しい場所で2~3カ月保存することが可能です。これは冷凍技術がなかった時代、かぼちゃは比較的長い期間保存が可能な食材でした。加えてビタミンやミネラル、カルシウム、食物繊維など栄養をバランスよくとれるので風邪を予防できるとされてきました。

②「冬至粥」を食べる
冬至粥とは、冬至の日に食べる粥で、一般的に小豆粥のことを指します。お祝いの日に赤飯を炊くように、昔から小豆の赤は邪気を祓うと言われているので、冬至粥で邪気を祓い、翌日からの運気を呼び込む縁起物とされてきました。
また、お粥の材料となる小豆は栄養価が高く、疲労回復、肩こりなどに効果があり、解毒作用もあります。寒さでエネルギーを奪われて体力が落ちてしまいがちなこの時期においてエネルギー補給となることでしょう。

③ゆず湯につかる
もう一つの冬至の風習は、ゆずを浮かべたゆず湯。この風習は江戸時代から始まったものです。
香りの強いユズを浮かべ、厄除けのための禊(みそぎ)として入るようになったという説と、 「ゆず」と「冬至」を、「融通(ゆうずう)」と「湯治」にかけているという説もあります。
ユズの皮には、代謝を円滑にして疲労回復効果のあるクエン酸や、ビタミンCが豊富に含まれていて、ゆず湯には血行促進や冷え性改善の効果があるとされ、その効能は科学的にも証明されています。
ゆず湯につかることで、「ひびやあかぎれなどの冬特有の肌荒れを防ぐ」「冬至の日に柚子湯に入ると風邪をひかない」と言われています。
香りもよいので、冬至の日には、ゆっくりゆず湯につかってリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

いかがでしたでしょうか?
あらゆる生命活動の源となるのが太陽。太陽の照る時間が最も短くなる冬至。昔から伝わってきた冬至の風習には、今みても健康の維持などに効果のあるものが残っています。
太陽や運気が盛り返すことを願い、一陽来復のご利益を求め、栄養のあるものをたっぷり食べて、気分も体調も上げて新年を迎える準備をしましょう!

recommended posts
-

vol.264 デトックスウォーターの効果とは?基本の作り方やおすすめ食材をご紹介
2022.09.30
-

vol.014 渋木さやかさんインタビュー第2回目 ワークスタイル=ライフスタイルを叶えるヨガが、気持ちの切り替えや自分を輝かせる秘訣に
2020.03.31
-

vol.410 美と愛の女神アフロディーテが創った香り「スイートマジョラム」。基本情報や効果効能をご紹介
2024.02.19
-
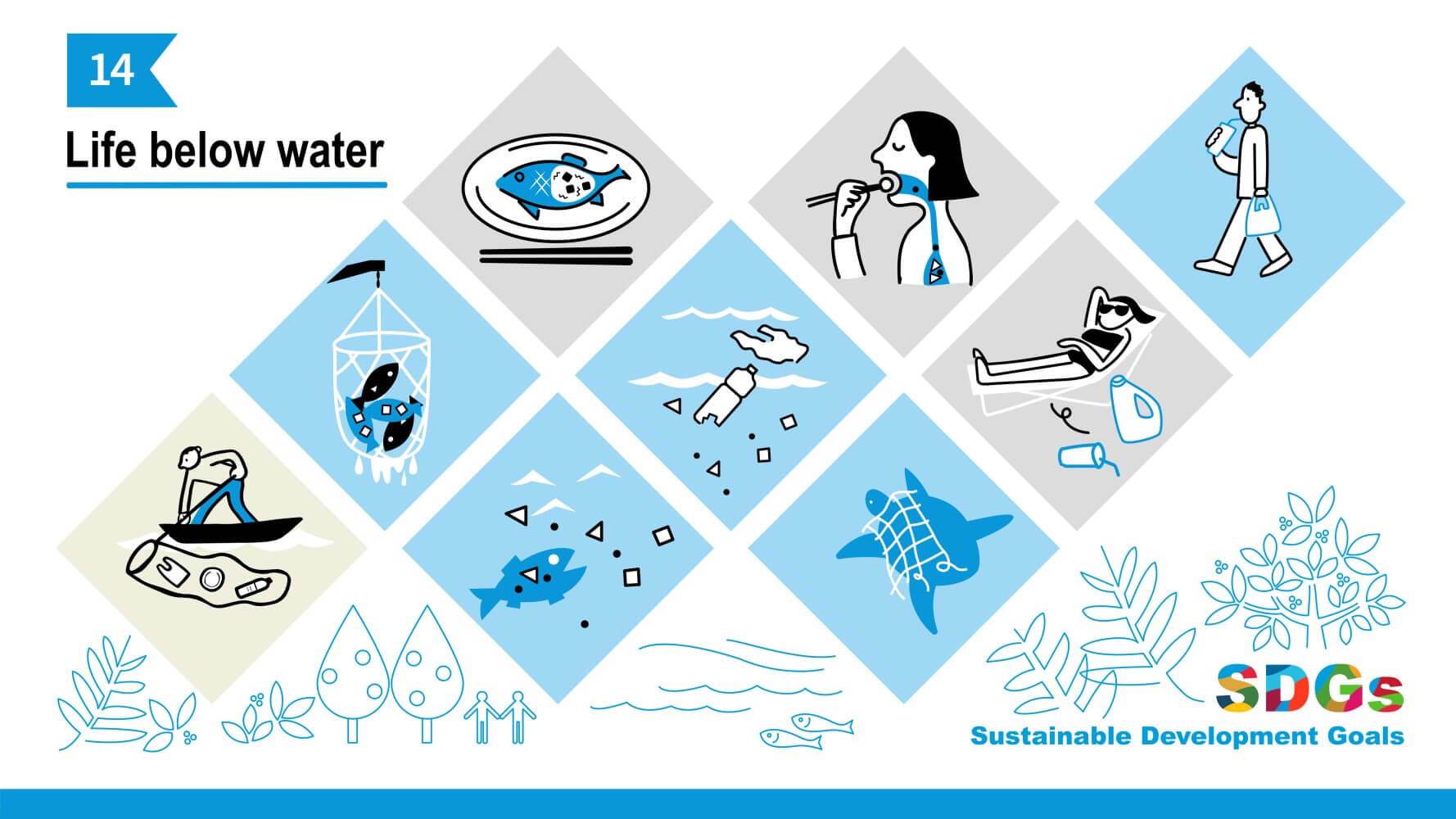
vol.532 豊かな海を次世代へ。SDGs目標14達成に向けた世界と日本の取り組み、そして私たちにできること
2025.06.23
-
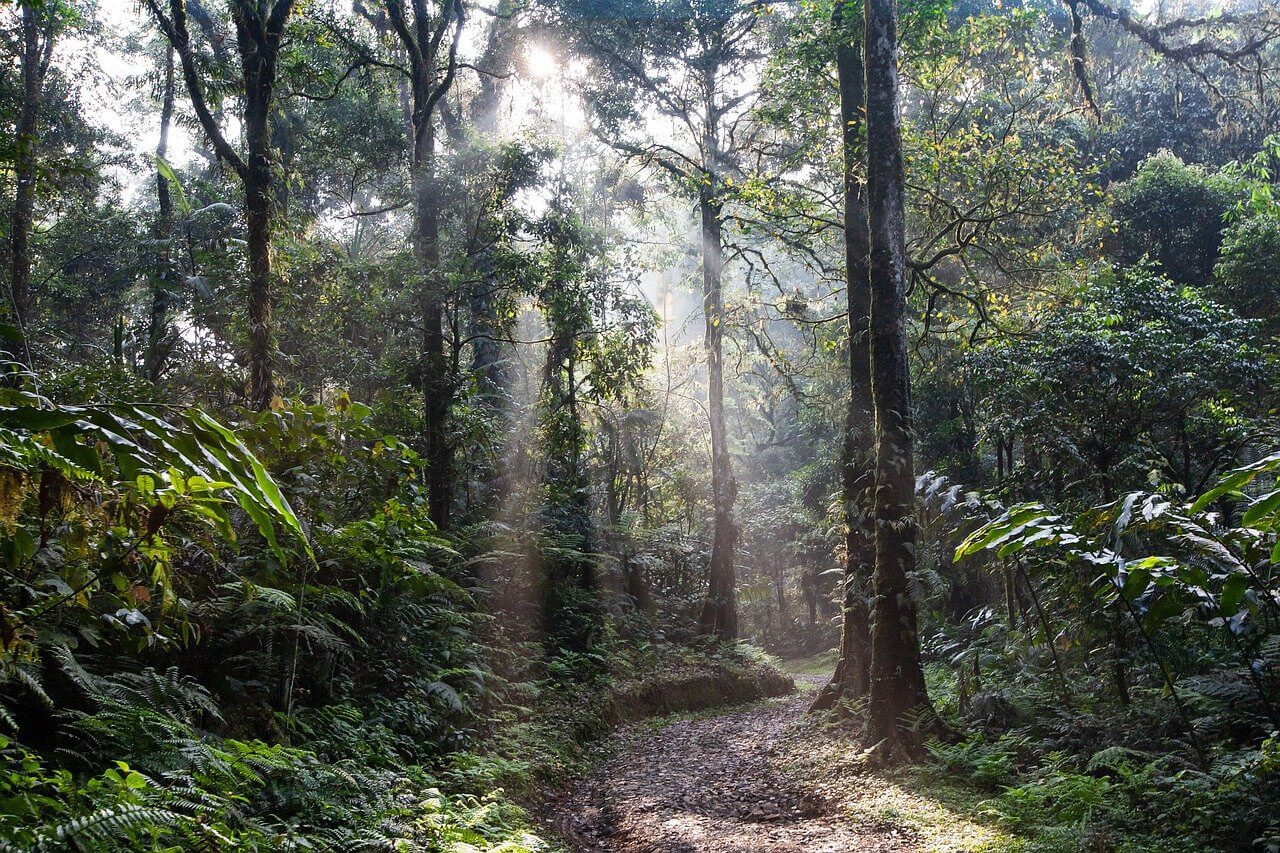
vol.063 プラスチックと環境問題について考える。あなたの生活の選択の一つから地球の未来を守ろう<後編>
2021.01.26
-

vol.439 古くから生薬として活用されてきた和ハーブ「ドクダミ」。日本の三大薬草の1つの「ドクダミ」が持つ魅力
2024.07.08
-

vol.466 今の枕はあなたに合ってる?枕が睡眠に与える影響と枕選びのコツ
2024.10.24
-

vol.016 田中里奈さんインタビュー 第1回目 余白をつくることで、豊かさの概念が変わった
2020.05.12
-

vol.457 基礎体温とは!?基礎体温で身体のリズムを知ろう
2024.09.19
-
vol.264 デトックスウォーターの効果とは?基本の作り方やお・・・
column | 2022.09.30
-
vol.014 渋木さやかさんインタビュー第2回目 ワークスタイ・・・
INTERVIEW | 2020.03.31
-
vol.410 美と愛の女神アフロディーテが創った香り「スイート・・・
column | 2024.02.19
-
vol.532 豊かな海を次世代へ。SDGs目標14達成に向けた・・・
column | 2025.06.23
-
vol.063 プラスチックと環境問題について考える。あなたの・・・
column | 2021.01.26
-
vol.439 古くから生薬として活用されてきた和ハーブ「ドク・・・
column | 2024.07.08
-
vol.466 今の枕はあなたに合ってる?枕が睡眠に与える影響と・・・
column | 2024.10.24
-
vol.016 田中里奈さんインタビュー 第1回目 余白をつくる・・・
INTERVIEW | 2020.05.12
-
vol.457 基礎体温とは!?基礎体温で身体のリズムを知ろう
column | 2024.09.19









